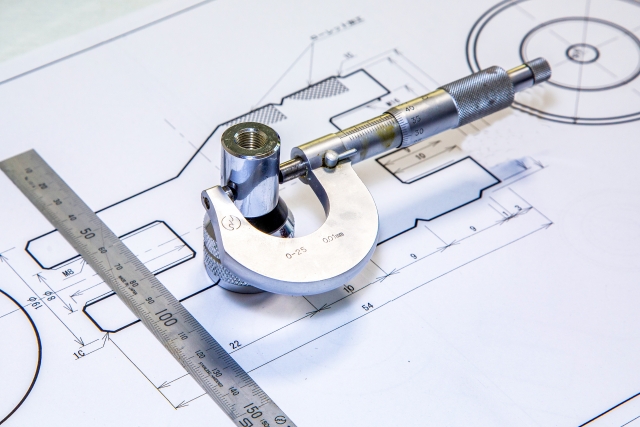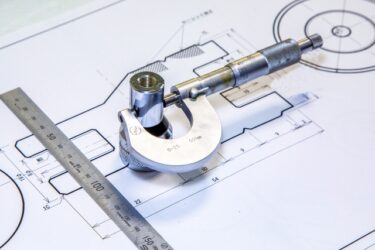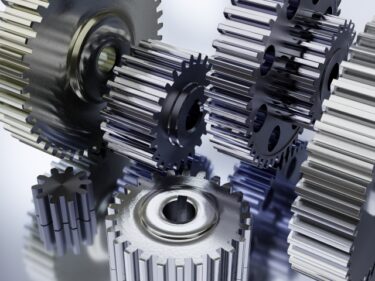機械設計技術者試験2級の具体的な勉強方法について解説します。
私はこの方法で、2021年に一発合格する事ができました。
機械設計技術者試験2級にチャレンジする方の参考になれば幸いです。
機械設計技術者試験とは?

「機械設計技術者試験」とは、日本機械設計工業会が運営する
機械設計者の技術力を認定する民間の資格試験です。
国家資格で有名な「技術士」とは異なる資格ですが、
機械設計の業界では有名な資格試験になります。
資格は1級、2級、3級に分かれており、本記事は2級の内容になります。
機械設計技術者試験2級の概要
受験する意味
合格すれば、機械設計に関する基礎知識を持っていて、
実務を任せて良いレベルにある事を証明できます。
会社によっては昇進に有利に働きます。
試験範囲が広いので、本番に向け勉強する中で
実務に役立つ知識が蓄積されていくと思います。
合否結果に関わらず機械設計者として成長できるはずです。
受験資格
申し込めば誰でも受験できる訳ではなく、受験資格が決められています。
専攻や学歴によって、3~7年の実務経験が必要です。
詳細は機械設計技術者試験を運営している
「日本機械設計工業会」の公式サイトをご覧ください。
試験方式と出題科目
基本はマークシート方式です。
問題によっては言葉を記述したり、溶接記号を記入する場合もあります。
また最終科目の「応用・総合」は記述式の問題となります。
出題科目は以下の通りです。
(2021年度から名称が変わり下記のようになりました。)
- 機械設計分野:機構学、機械要素設計、機械製図、関連問題
- 力学分野:機械力学、材料力学、関連問題
- 熱・流体分野:熱工学、流体工学、関連問題
- 材料・加工分野:工業材料、工作法、関連問題
- メカトロニクス分野:制御工学、デジタル制御、RPA、自動化技術、他
- 環境・安全分野
- 応用・総合
難易度と合格点
計算問題の難易度は、大学で習った4力学の基礎が頭に入っていれば
全く問題ないレベルです。
ただ暗記科目のボリュームも多いので油断は禁物です。
難易度を他の資格と比較すると、
「技術士一次試験より少し難しいくらい」と言われています。
合格点は公表されていませんが6割程度解ければ安全だと思います。
「点数ではなく受験者全体の割合で合否を決めているのではないか」、
「正答率の悪い科目が2科目以上あると不合格なのではないか」、
などの噂もありますが正確な事は運営にしか分かりません。
日程、受験料
試験日は毎年11月下旬の休日です。
時間割は130分、120分、90分の3コマ構成です。
これらを1日で終わらせるため、朝~夕方まで試験が続きます。
受験料は税込22,000円です。
補助が出る会社もありますが個人負担だと手痛い出費です。
おすすめの勉強方法
本題の勉強方法について説明します。
私はこの方法で2021年に一発合格する事ができました。
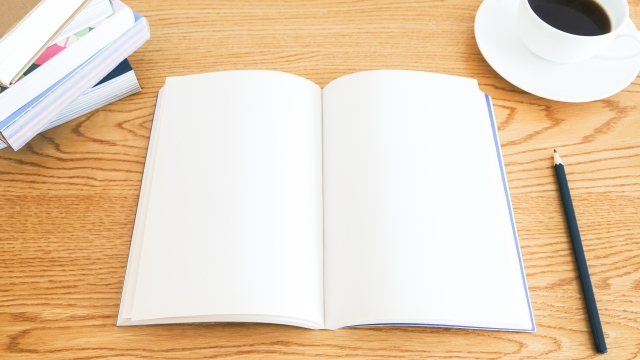
総勉強時間
大学で機械系の専攻、かつ機械設計の経験が3年ほどある人で、
「総勉強時間150時間」が目安です。
平日1.5時間を週4回(平日1日は休憩)、休日3時間を週2回、
これを3ヶ月続ければ約150時間になります。
試験本番は11月下旬なので勉強期間を3ヶ月確保すると、
盆明けの8月下旬くらいから勉強をスタートするイメージです。
専攻が機械系でない等で前知識が無い人は、
200~300時間掛かるかと思います。
1週間あたりの勉強時間を増やすか、
勉強スタートの時期を前倒しして調整しましょう。
使用した参考書(この2種類だけでOK)
機械設計技術者試験 問題集(日本理工出版会)
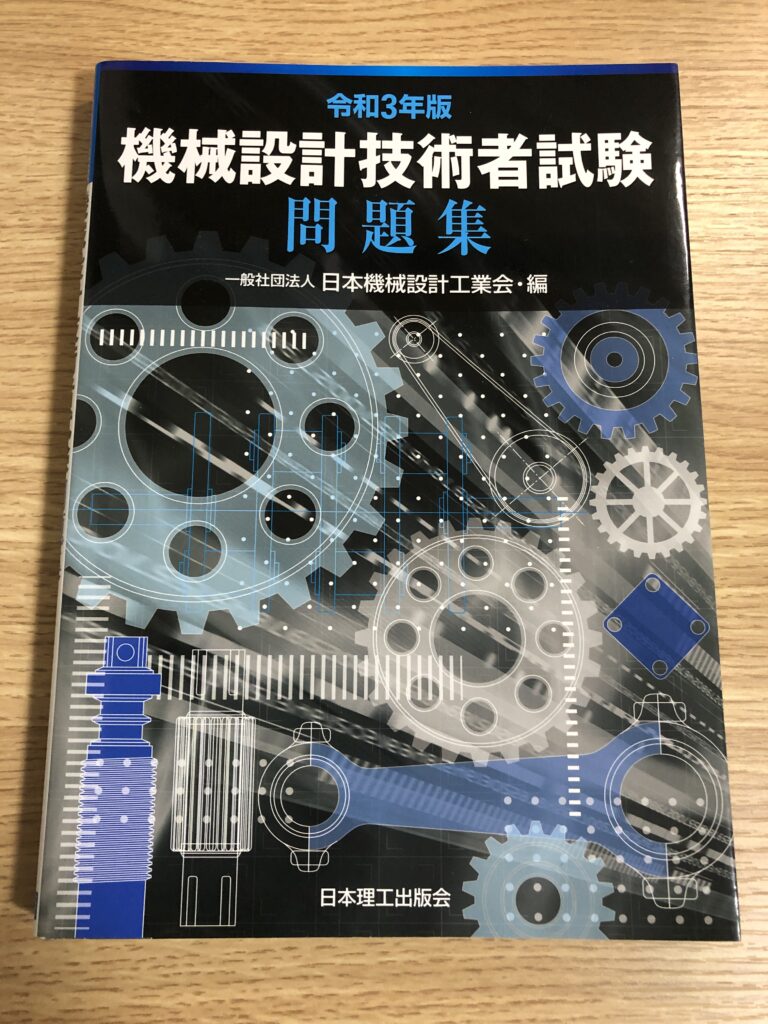
1冊につき1年分の1~3級の過去問・解答・解説がまとめられています。
問題と解答だけであれば、日本機械設計工業会の公式サイト
からダウンロードできますが、解説も欲しい場合はこの問題集を購入するしかありません。
解けなかった問題は解説を読んで理解する事が重要で、
これを怠ると同じ失敗を繰り返し、本番でも間違えます。
従って解説付きのこの問題集は、合格のためには必須のアイテムと言えます。
なお、試験対策は過去問をたくさん解く事が重要です。
できれば5年分くらい入手しておきたいですが、
1冊3,000円もするので何冊買うかはお財布と相談になります。
過去の受験生で問題集を持っている知り合いがいれば借りると良いでしょう。
書店に置いていない事も多いので、ネットでの購入がおすすめです↓
ちなみに2022年版から出版社が変わり、表紙のイメージが変わっているようです。
著者が同じなので、内容はこれまでと同じだと思われます↓
機械設計技術者のための基礎知識(日本理工出版会)
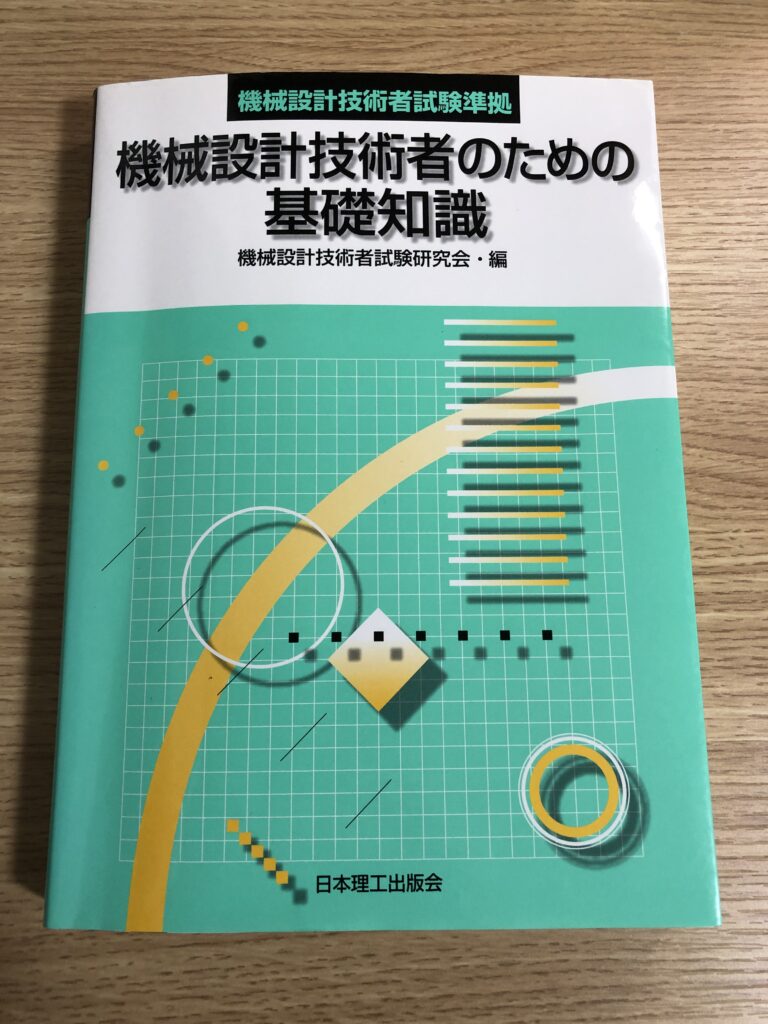
全科目の基礎知識・公式・練習問題がまとめられており、
この1冊で試験範囲を広く浅く勉強する事ができます。
科目ごとに別々の参考書を買っても良いですが、
機械設計技術者試験は試験範囲が広いので、時間がいくらあっても足りません。
この参考書は試験で頻出する箇所がまとめられているので、
効率よく合格するには必須のアイテムと言えます。
ただし全ての範囲が網羅されている訳ではなく、
この参考書に書かれていない内容もバンバン出てきます。
最低限この程度は知っておこう、という内容であることをご認識置きください。
過去問を解き始める前に一通り読んでおく事をお勧めします。
こちらも書店に置いていない事も多いので、ネットでの購入がおすすめです↓
具体的な勉強方法
4つのステップに分けて勉強したので、順番に説明します。
- 過去問を1年分を眺めて、勉強のゴールを知る
- 「機械設計技術者試験のための基礎知識」を一通り読む
- 過去問をひたすら解く(3~5年分程度)
- 暗記科目の仕上げ
①過去問を1年分を眺めて、勉強のゴールを知る
本格的に勉強をスタートする前に、
適当な年の過去問を1年分を眺めてみましょう。
この段階では真面目に解く必要はありません。
どのレベルの問題が出題されているのかを把握する事で、
勉強のゴールを知るのが目的です。
今の自分の知識で何割程度解けそうかによって、
必要な勉強時間もおおよそ分かります。
参考までに私の場合は「ノー勉で3~4割くらい解けそうかな?」
という感覚で、150時間ほど勉強して合格できました。
②「機械設計技術者試験のための基礎知識」を一通り読む
いきなり過去問を解き始める方法でも良いですが、
基礎知識が無い状態で挑んでも勉強の効率が悪くなります。
まずはこの参考書を一通り読んで、基礎知識を身に付けておきましょう。
出題範囲を広く浅く勉強する事ができます。
読む際の注意点は以下の通りです。
- 主要な公式は全て覚える
- ただし導出方法や式展開まで細かく追う必要は無し。
時間が掛かり過ぎる上に、そこまで出題されないため。 - 材料、工作法、製図などの暗記科目はどうせ1回で覚えられないので、
本番まで何度も読み直すつもりで、最初の1回目は適当に読み飛ばす。 - 全体を通して「どのページにどの情報が載っていたか」が頭に入ればOK
私の場合は公式の導出方法まで真面目に読んでしまったので、
予想外に時間が掛かり、読破に1.5ヶ月ほど要しました。
勉強にはなりましたが、試験に合格するだけなら
そこまで真面目に読む必要が無かったと反省しています。
③過去問をひたすら解く(3~5年分程度)
基礎知識を身に着けたら、過去問をひたすら解きます。
最低3年分は解く事をお勧めします。
5年分もやれば初見の問題もだいぶ減り、安心して本番に臨めるでしょう。
前半の数年分は制限時間を気にせず解き、自分の知識が足りているかチェックします。
後半の数年分は本番同様の制限時間で解く事をオススメします。
本番は時間との勝負になるので、時間配分の感覚を掴んでおくと良いです。
合格点は公表されていませんが、おそらく6割程度なので、
本番までに「制限時間内で安定して6~7割解ける」仕上がりを目標にしましょう。
過去問で間違えた問題は、解説もしっかり読みます。
また、頻出する公式などの重要なポイントは勉強ノートを作ってまとめておくと良いです。
この勉強ノートを作った事が、試験勉強で一番役に立ったと感じています。
メリットを挙げると以下の通りです。
- 重要なポイントをいちいち参考書を調べて思い出す手間が省ける
- ノートに書く事で記憶に定着し易い
- 試験の直前でソワソワする時も、ノートを見直せばよい、と安心できる
- 試験が終わった後も、実務で「あの公式なんだっけ」となる時に役立つ
少し面倒な作業かもしれませんが、
最終的には勉強ノートを作って良かったと思えるはずです。
是非お試しください。
④暗記科目の仕上げ
材料、工作法、製図などの暗記科目は出題範囲が広いので、
試験本番まで参考書を何周も読まないと記憶が定着しません。
過去問を一通り解き終わり計算科目に慣れてきたら、暗記科目に力を入れましょう。
しっかり勉強すれば得点源になります。
試験本番での注意点
試験本番での注意点を2つほど紹介します。

時間配分
時間に追われる前半2コマは、時間配分が重要です。
1コマあたり3科目ですが、単純に3等分の時間ずつ使って回答すれば良い、
という考えは危険です。
最後に見直しする時間や、分からなくて飛ばした問題を解きに戻る時間を考慮して、
時間配分を考えましょう。
「応用・総合」科目
最後の1コマは時間が十分ある代わりに、内容が難しいです。
さっぱり分からなくても、合っている自信がなくても、
とりあえず何か書きましょう。
導出過程まで書かせる問題なので、途中の式が何かしら合っていれば、
部分点をもらえるはずです。
私も応用・総合は全く自信が無く半分以上空白で出した記憶がありますが、
ちゃんと合格できましたので、ご安心ください。
試験後
試験から約一ヶ月後に、メールで合否の連絡が届きます。
無事に合格すれば認定証とライセンスカードが郵送されます。
不合格の場合は、日本機械設計工業会のマイページに、
各科目の得点率がザックリと分かる「科目別5段階評価表」が公開されます。
(合格者には公開されません。)
どの科目を何割得点できたかが分かりますので、
再チャレンジする際の参考にしましょう。
まとめ
機械設計技術者試験2級の勉強方法について解説しました。
オススメの勉強方法は以下の通りです。
- 過去問を1年分を眺めて、勉強のゴールを知る
- 「機械設計技術者試験のための基礎知識」を一通り読む
- 過去問をひたすら解く(3~5年分程度)
- 暗記科目の仕上げ
機械設計技術者試験2級にチャレンジされる方は是非参考にしてください。
皆様の合格をお祈りしています。